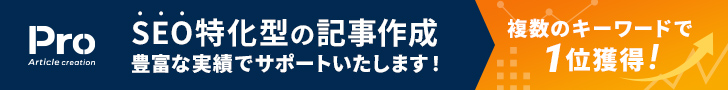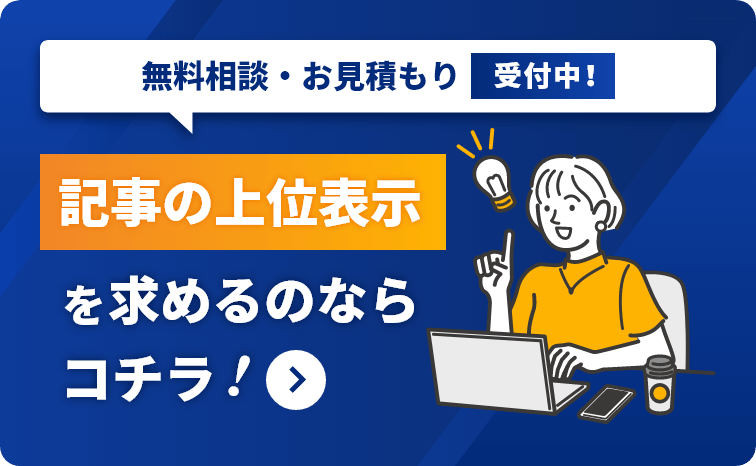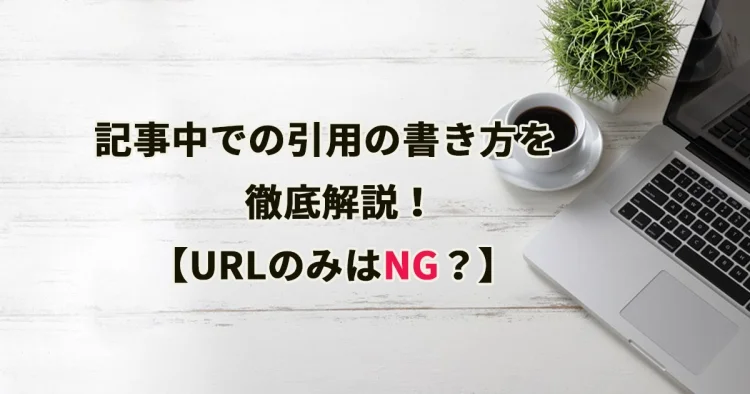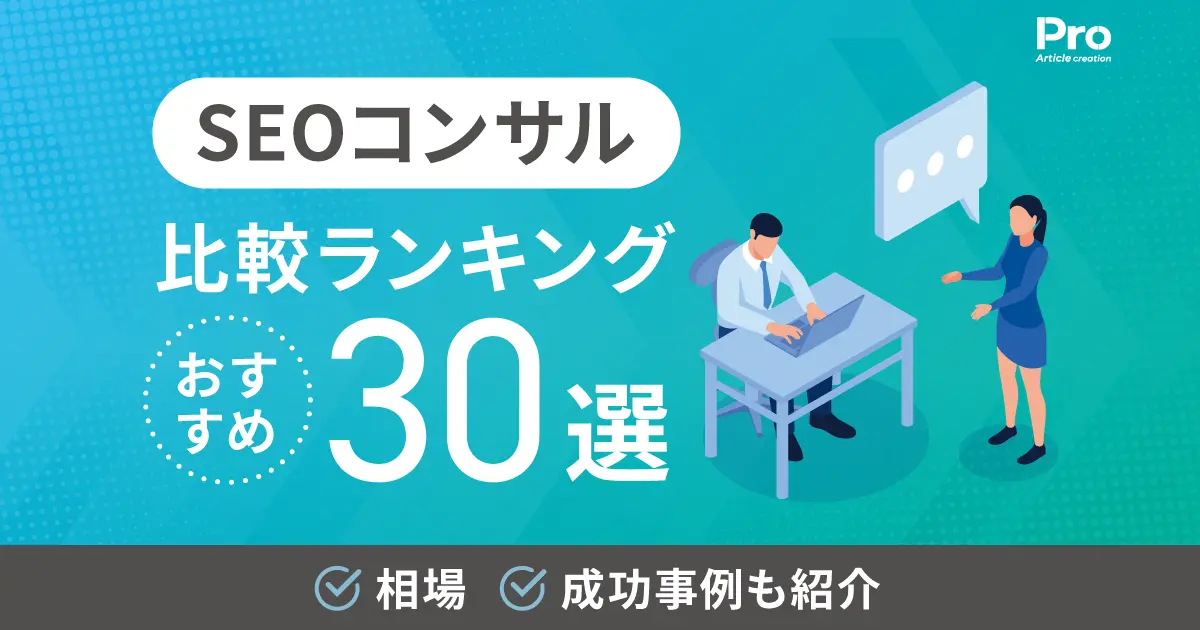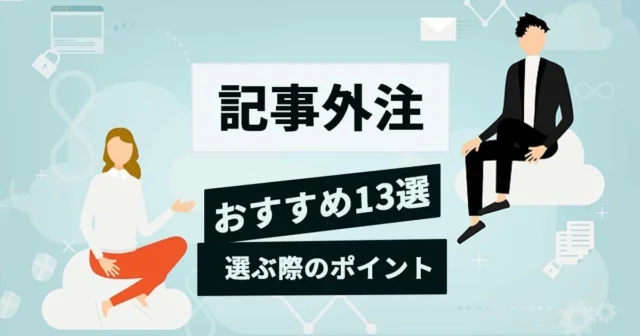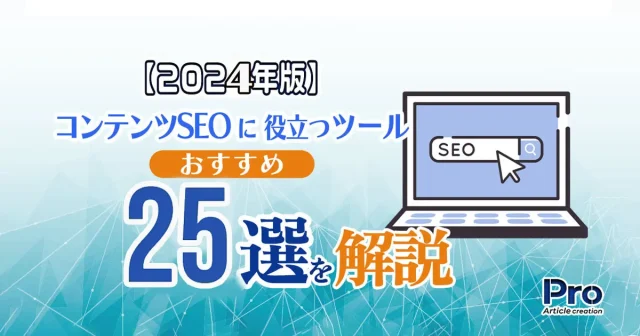【コンテンツマーケティング】SEO対策と文字数の真の関連性とは?
- 公開日:2023.03.23
- 更新日:2024.05.27
- コンテンツマーケティング
「ロングコンテンツの方が上位表示を狙える」
以前は、コンテンツマーケティングにおいて、文字数は有意に影響を与えるものと認識されていました。
しかし、アルゴリズムアップデートを経て、コンテンツの文字数よりも網羅性や専門性、ユーザビリティなどが重視される時代へと変わりつつあります。
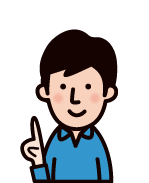

スタッフ
目次
1.【結論】コンテンツマーケティングにおいて重要なのは「文字数」より「ユーザー目線」

結論、コンテンツマーケティングにおいて重要な役割を担うSEO(検索エンジン最適化)に関していえば、文字数自体が検索順位に直接的な影響を与えることはありません。
日本の検索シェアの9割以上を占めるGoogleの評価基準に文字数の規定はなく、「ユーザーのニーズに合致する情報か」「有益な情報を提供できているか」など、ユーザーが検索エンジンに入力する検索クエリに対する十分な回答が得られるかが重要とされています。


スタッフ
コンテンツSEOについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。
参照:「記事コンテンツの書き方大全!CVアップにつながる6つのポイント」
2.2つのアルゴリズムアップデートで変化したコンテンツマーケティングにおける文字数の概念

スタッフ


スタッフ
2-1.大規模アップデート以前|ロングコンテンツが評価される

パンダアップデートは2011年、ペンギンアップデートは2012年~2016年にかけて行われた大規模なアルゴリズムアップデートです。
2016年頃までのGoogle検索では、長文のコンテンツが評価され上位表示されやすい傾向にあったため、上位サイトがロングコンテンツで埋め尽くされていました。
1万文字を超えるものも珍しくなく、内容が薄いにもかかわらず、ドメインパワーやwebサイトの規模の大きさを理由に検索上位に上がるケースも非常に多く見受けられました。
2-2.大規模アップデート以降|高品質な記事が評価される
2011年以降繰り返し行われたアルゴリズムアップデートにより、長文であることを理由にコンテンツが評価される時代に終止符が打たれました。
2011年、低品質なコンテンツを検索上位から排除する目的で行われたパンダアップデートによって、ボリュームのみに頼った内容の薄いコンテンツが淘汰され始めます。
そして、2012年~2016年ペンギンアップデートにより、意図的な被リンク対策や過剰なSEO対策を施したwebサイトの評価が下げられ、高品質なコンテンツが検索エンジン上で正しく評価されるようになりました。
現在もアルゴリズムをかいくぐった悪質なコンテンツが上位表示されないよう、大小さまざまな規模のアップデートが繰り返されています。
3.【コンテンツマーケティング】文字数の多いサイトがSEOに強いとされる理由


スタッフ
3-1.情報の網羅性

コンテンツ内に検索意図に合致する情報が多く盛り込まれているほど、ユーザーの悩みを解消できる可能性が高まるため、高品質であると評価され、検索上位に表示されやすくなります。
また、Googleの評価基準として明記されている項目の一つである「独自性がある専門的な記事」を作成するには、ユーザーにとって有益性が高く競合のコンテンツには含まれていない情報をプラスする必要があります。
以上のことから、有益な情報を盛り込むことによるロングコンテンツ化は必然的といえるでしょう。

スタッフ

3-2.キーワードや共起語の量
文字数を増やせば、必然的に単語数が増加するため、キーワードや共起語を盛り込みやすくなります。
これによって、いくつかのキーワードを組み合わせた複合キーワードがコンテンツ内に増えることで、アクセス量は少なくてもコンバージョン(webサイトで得られる効果)につながりやすいロングテールアクセスが増える可能性が高まります。
3-3.文字情報の優位性

Googleのアルゴリズムでは、コンテンツ内の画像の中の文字や人の表情を認識し、その情報を言語化して評価しています。
よって、トップ画像やキャプチャの変更で順位が変動するケースもあります。
ただ、画像の意味や動画内容の把握の精度は、文字情報に比べ劣るため、正確な評価を受けにくいのが事実です。
そのため、画像や動画を挿入してユーザビリティの向上をはかりつつ、検索意図に合ったキーワードを盛り込んだり、文字で適宜解説を加えたりする必要があります。
3-4.滞在時間の増加
ユーザーのニーズを満たしたロングコンテンツは、読み進めるのにある程度の時間を要するため、ページの滞在時間が長くなる傾向にあります。


スタッフ
4.文字数のみにとらわれない!コンテンツSEOで重視すべき7つのポイント


スタッフ
4-1.ニーズに合った文字数

文字数は、検索ニーズに合った最適なボリュームに設定しましょう。
ビックキーワード(検索ボリュームが多いキーワード)であれば、情報の網羅性のある記事が有利になるため、必然的にロングコンテンツになります。
一方、ロングテールキーワード(複数のキーワードを組み合わせた検索ボリュームの少ないキーワード)はニーズが絞られるため、情報を絞り込んだ読みやすい記事が好まれます。


スタッフ
4-2.競合サイトの把握
必要な文字数や情報量は、検索上位にある競合サイトを調査することで、ある程度把握できます。
競合サイトの文字数が5,000文字であった場合、検索上位に表示させるためには、そのサイトを上回る網羅性や専門性のある内容でコンテンツ作成する必要があるため、当然文字数も同等、またはそれを上回る必要があると判断できます。
4-3.網羅性



スタッフ
4-4.検索意図と合致した内容
記事を読んでいる途中で湧いた疑問が解決されなければ、ユーザーは途中で離脱してしまいます。
つまり、ユーザーが求めている内容に加え、想定される疑問に対する解決策を示し、「痒いところに手が届く」コンテンツを作ることが、SEO対策において重要となります。

スタッフ
4-5.ユーザビリティ


スタッフ


スタッフ
4-6.E-E-A-T
Googleの「検索品質評価ガイドライン」には、コンテンツとサイトの評価の基準として以下の項目が明記されています。
- Experience(経験):実体験に基づく一次情報
- Expertise(専門性):専門知識を含む内容
- Authoritativeness(権威性):専門家が作成あるいは監修したコンテンツ
- Trust(信頼性)信用できる公的機関の情報
もともと「E-A-T」として知られていましたが、2022年12月15日に新たにExperience(経験)が追加され「E-E-A-T」となりました。
SEO対策とともに「E-E-A-T」を満たしたコンテンツ作成を行うかどうかが、今後の検索順位を大きく左右するでしょう。
「E-E-A-Tの詳しくはこちら」
4-7.サイト構造
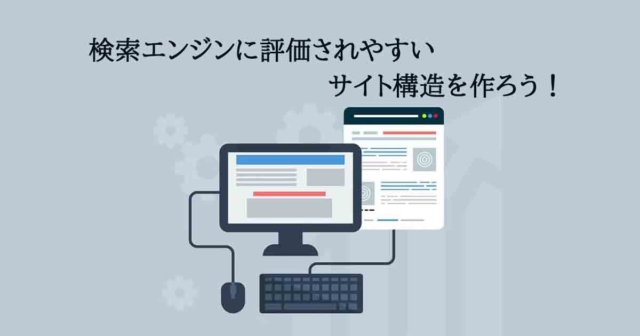

スタッフ
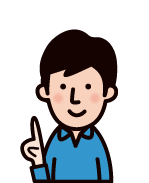
5.まとめ
コンテンツマーケティングにおいて、文字数は最重要項目ではありません。
ユーザーの悩みを解決に導くために必要な情報を網羅した結果、文字数がかさむことはあっても、文字数稼ぎの内容の薄いコンテンツは、検索エンジンによって淘汰されます。
今後コンテンツマーケティング、コンテンツSEOに取り組む際は、ご紹介した7つのポイントに注目し、ユーザー目線に立った良質なコンテンツ作成を心がけましょう。
関連記事
-
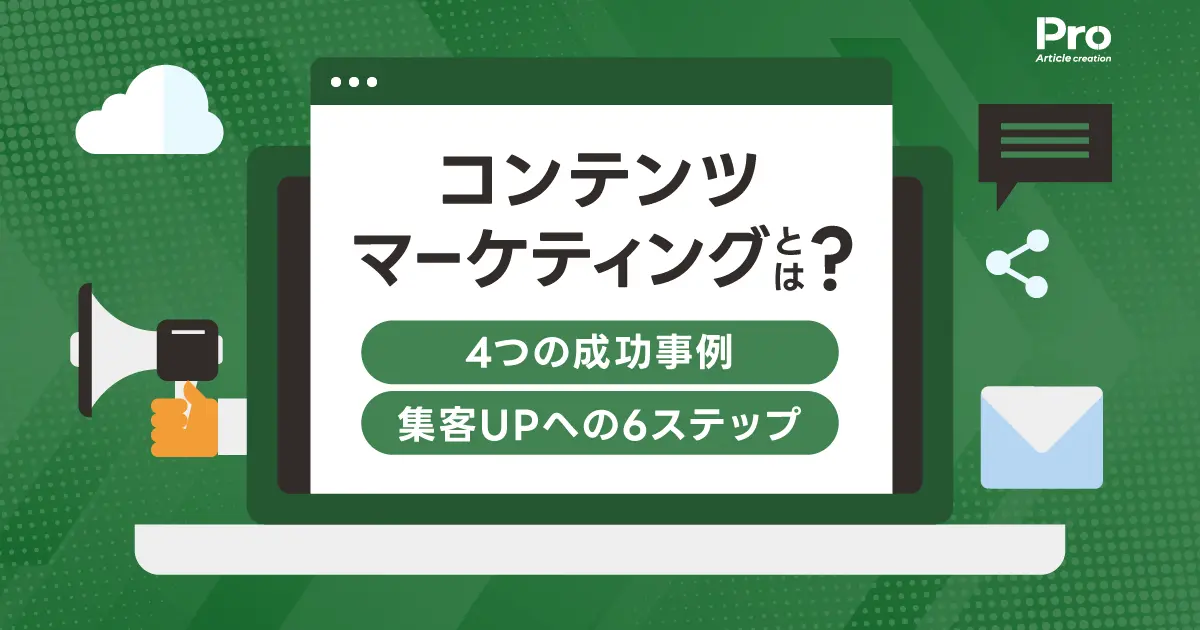
2024.07.18
コンテンツマーケティングとは?4つの成功事例・集客UPへの6ステップ戦略も解説!
「コンテンツマーケティングとはなに?」 「戦略立案の方法が知りたい」 コンテンツマーケティングを検討する上で、上記のようなお悩みはないでしょうか? 結論、コンテンツマーケティングは、多くの顧客を獲得できる手法ですが、長期的な計画が必要です。 そこで本記事では「コンテンツマーケティングとはなにか」を深掘りするとともに、以下のテーマにも焦点を当てて解説していきます。 コンテンツマーケティングの種類 コ …
- コンテンツマーケティング
-
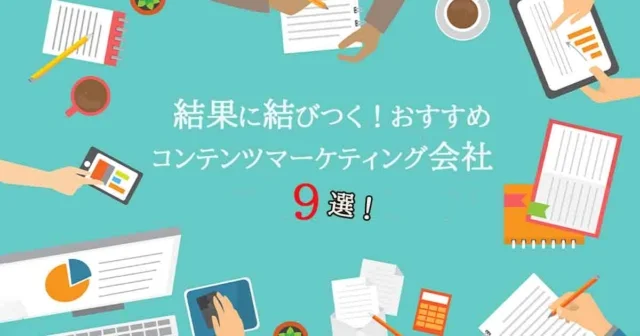
2024.04.12
結果に結びつく!おすすめコンテンツマーケティング会社9選
コンテンツマーケティング会社は、戦略設計からコンテンツ制作・分析まで、さまざまなサービスを手がけます。 コンテンツマーケティングのプロに業務を依頼すると、リソースが限られた状態で内製するよりも、ずっと効率的に成果を得られます。 そこでこの記事では、コンテンツマーケティング会社のおすすめ9選をご紹介。 また、会社の選び方や依頼するメリット・注意点も取り上げます。 コンテンツマーケティングを新規で始め …
- コンテンツマーケティング