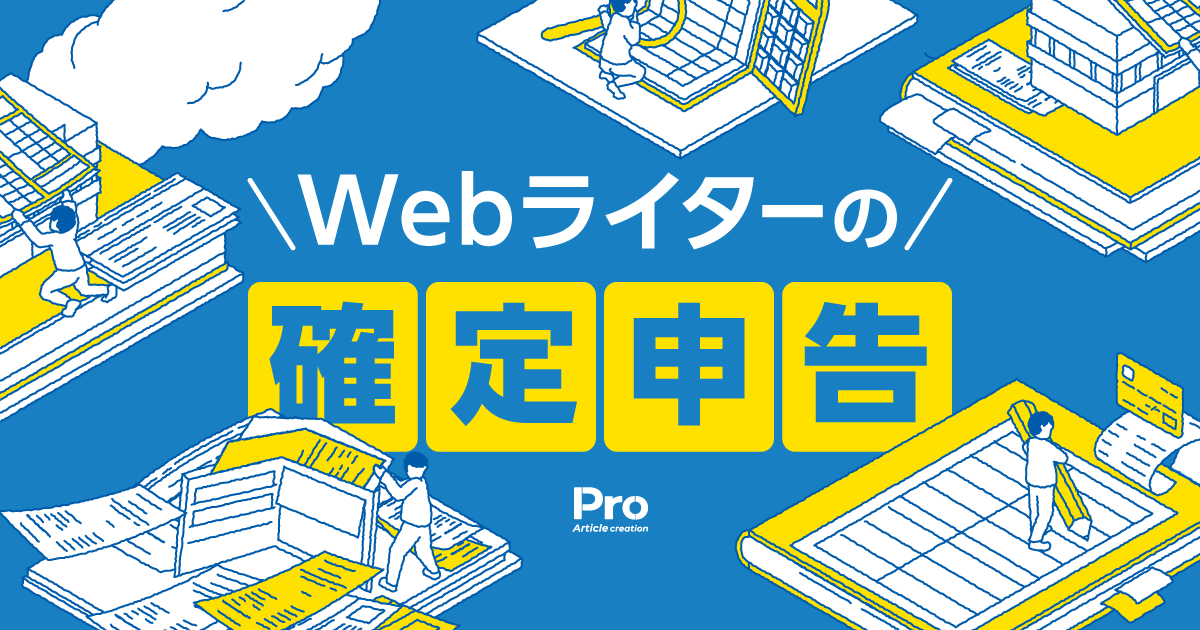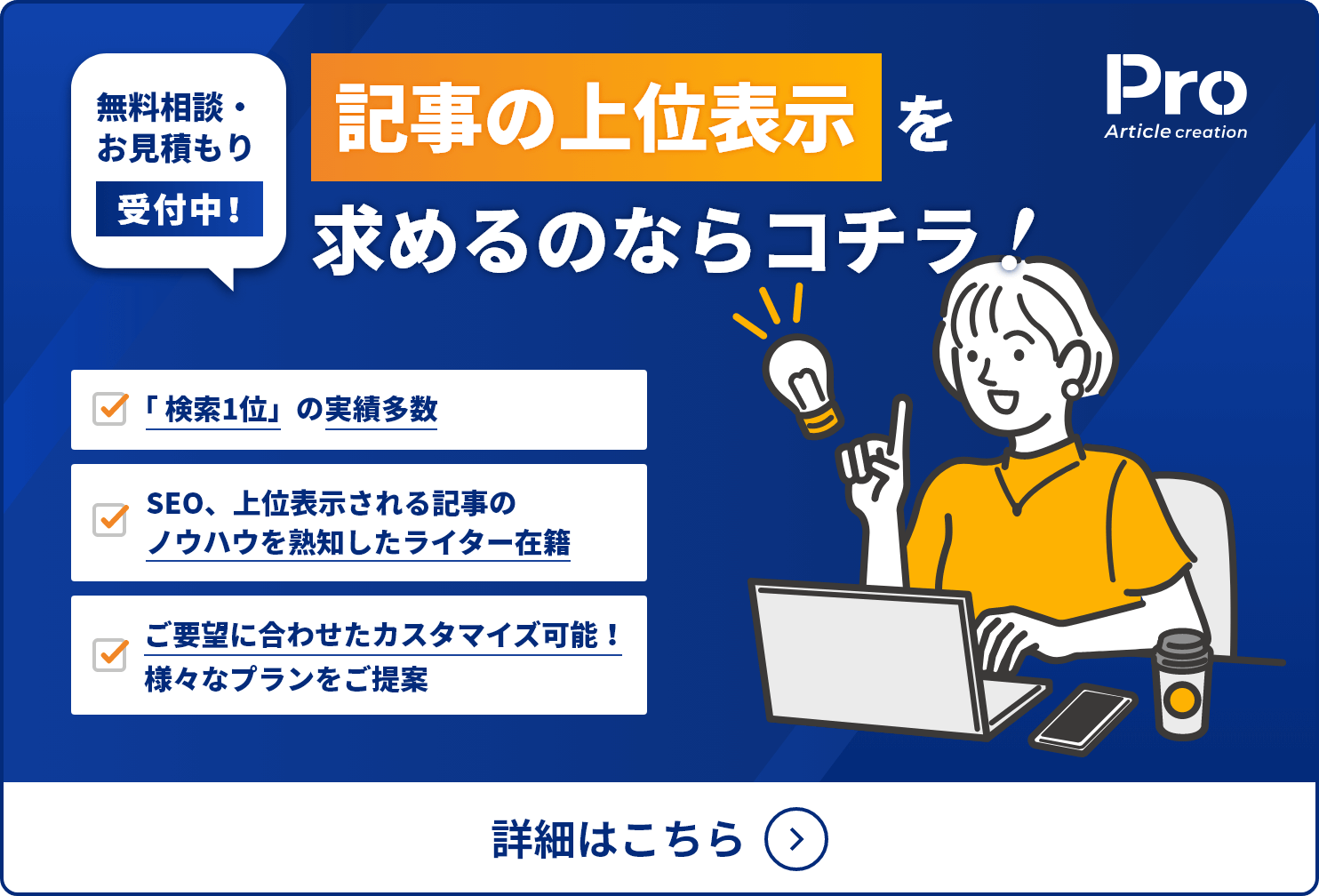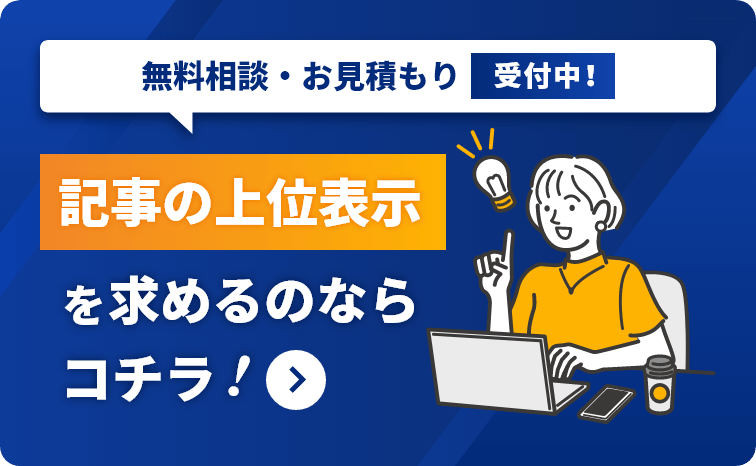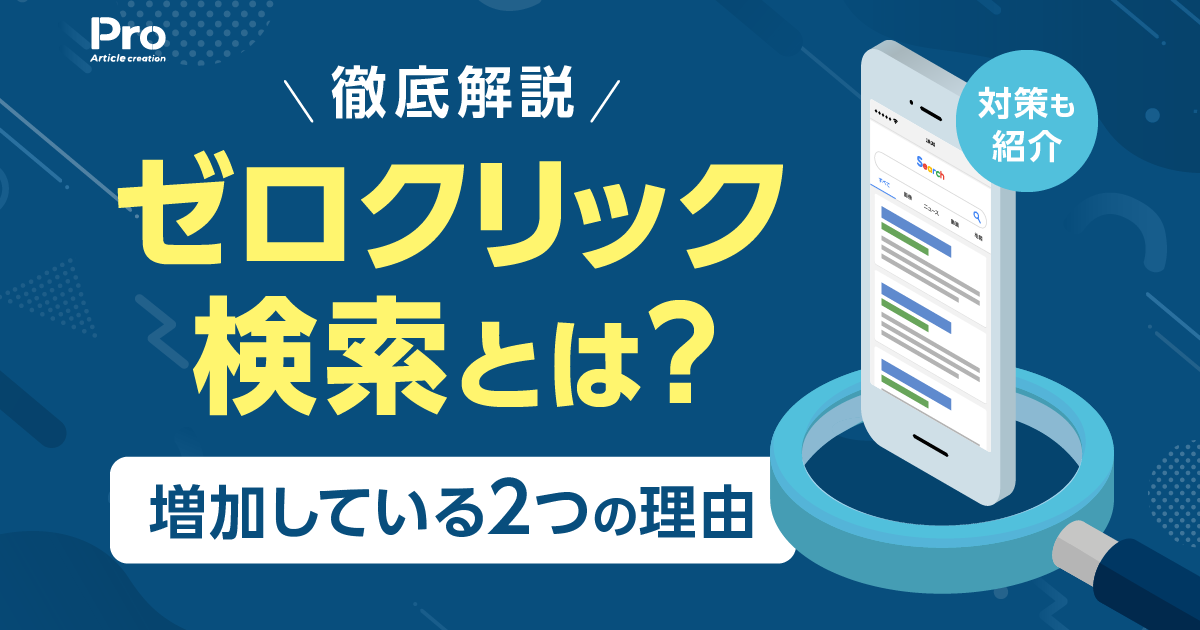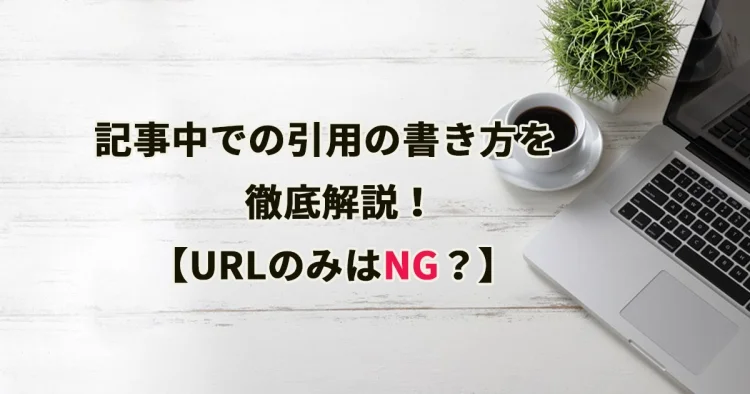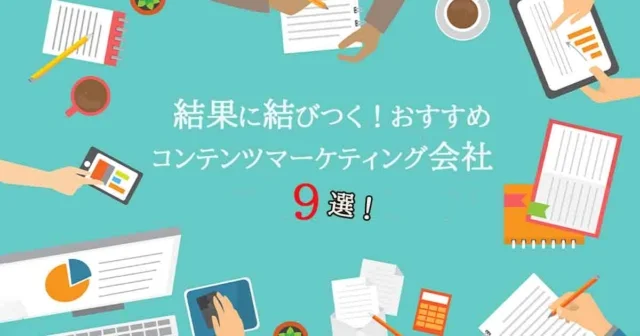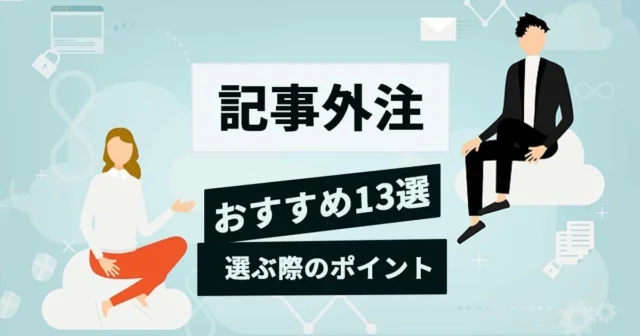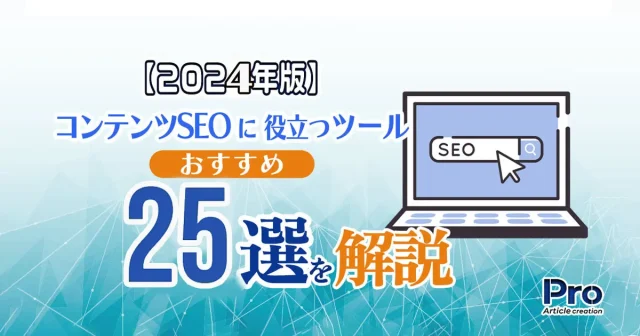Webライターに確定申告は必要!手順3Stepや経費に計上できるものも解説
- 公開日:2025.08.28
- 更新日:2025.08.28
- webライター
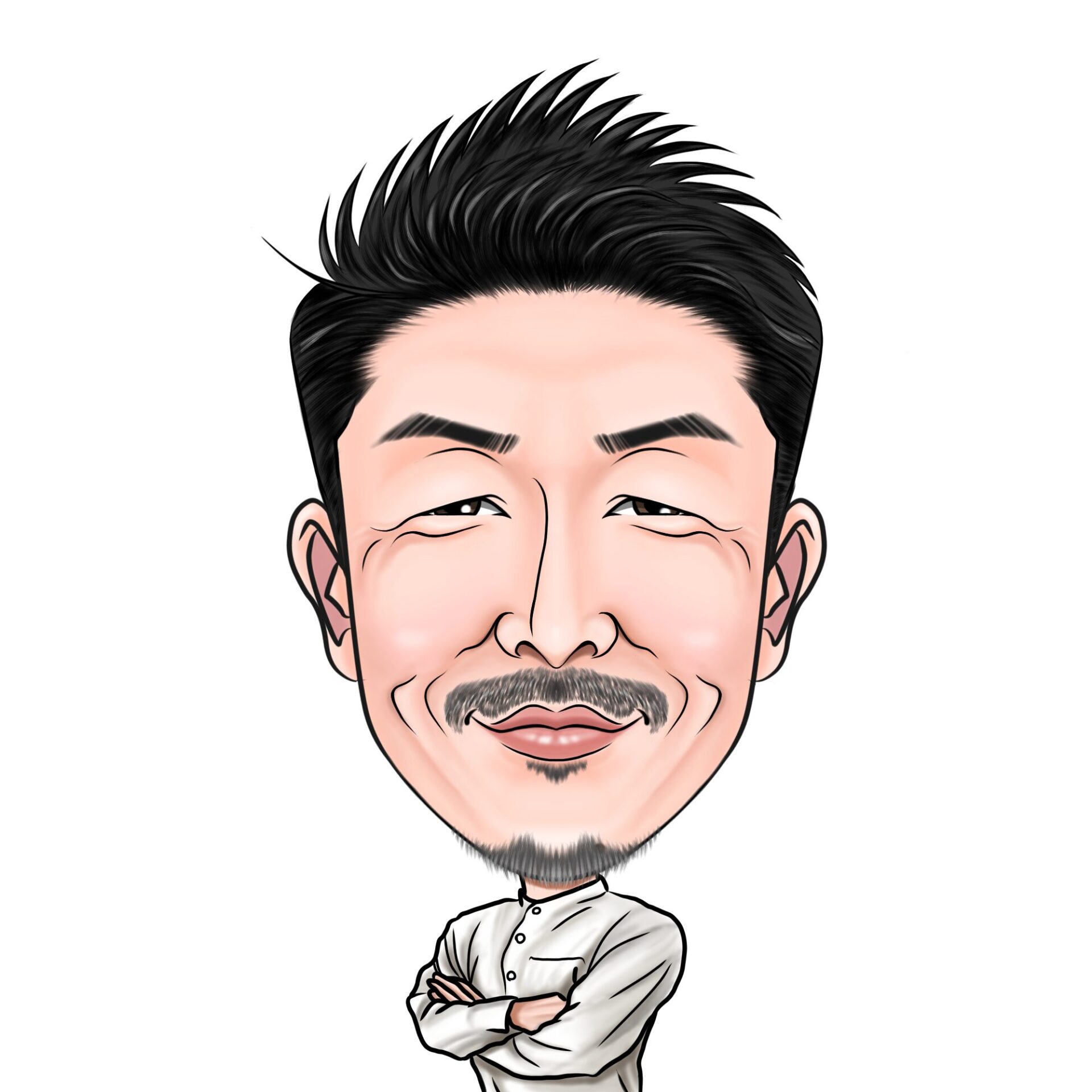
-
田端 健一
株式会社BRIDGEA 代表
-
- 通信業界の営業に10年携わり、多くの商品で営業成績日本一を獲得
- 独立して「記事作成代行Pro」を運営
- 「コンテンツマーケティング」や「コンテンツSEO」「記事作成代行」を行なっています。
- 多くのお客様サイトを上位表示に成功。今ではリピート案件多数
「所得はいくらになると確定申告が必要?」
「どのようなものを経費に計上できる?」
上記のような悩みを抱えている方は少なくありません。
Webライターとして活動するなら、本業であっても副業であっても、確定申告や税金の知識は不可欠です。
そこでこの記事では、Webライターに確定申告は必要なのか、Webライター向けの税金の基礎知識、経費計上のポイントまで、具体例とともに分かりやすく解説します。
安心してライティングを続けるための実践ガイドですのでぜひ最後までお読みください。
目次
1. Webライターに確定申告は必要?副業・本業の基準

Webライターが確定申告を行うかどうかは、所得の金額と、副業か本業かで決まります。
以下で基準を解説します。
1-1. 【副業Webライター】所得20万円超で確定申告が必要
副業でWebライティングを行う場合、年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
所得とは、クライアントからの報酬(収入)から経費を差し引いた金額をいいます。
例えば、年間報酬50万円で、パソコン購入費10万円と通信費5万円を計上した場合、所得は35万円(50万円-15万円)となり、20万円を超えるため確定申告が必要です。
なお、所得が20万円以下なら確定申告は不要ですが、住民税の申告は市区町村で必要です。
クライアントからの報酬には通常10.21%の源泉徴収が適用されますが、確定申告で還付を受けられる可能性があるため、確認するとよいでしょう。
1-2. 【本業Webライター】所得48万円超で確定申告が必要
本業でWebライティングを行う場合、年間の所得が基礎控除の48万円を超えると確定申告が必要です。
例えば、年間報酬100万円で、パソコン20万円と通信費10万円を計上した場合、所得は70万円(100万円-30万円)となり、48万円を超えるため確定申告が必要になります。
所得が48万円以下なら、税金はかからず確定申告も不要です。
また、青色申告を選べば赤字を繰り越せるため、申告を検討すると節税につながる場合があります。
2. Webライターのための税金・確定申告の基礎知識

確定申告を始める前に、税金の基礎知識を押さえておくと理解が深まります。
なぜ税金知識が必要か、報酬と税金の関係、確定申告の目的を以下で解説します。
2-1. Webライターに税金の知識が重要な理由
Webライターにとって税金の知識は、手元に残る報酬を最大化し、税務トラブルを防ぐために不可欠です。
ライティング業務では、記事単価やプロジェクト単位で受け取る報酬が所得税の対象となり、通常所得税(10%)と復興特別所得税(0.21%)を合わせて10.21%が源泉徴収されます。
例えば、月10万円の報酬で年間120万円稼ぎ、パソコンや取材費を経費として計上すると、その経費を差し引いた額が課税対象です。
適切な確定申告を行うことで、源泉徴収された税金の一部が還付されたり、医療費控除やふるさと納税を活用して節税できたりします。
また、申告漏れは追徴課税のリスクがあります。控除される額以上の所得を得ていたのに申告を怠ったことが税務調査で発覚すると、元々の税金に加え延滞税や無申告加算税(最大15~20%)が課される可能性があるので注意が必要です。
無申告のペナルティは他人事ではありません。
実際に、国税庁の調査によると、令和5事務年度の所得税調査で申告漏れ所得金額は9,964億円にも上り、その結果1,398億円の追徴課税が課されました
こうした税金トラブルを回避するためにも、税金の知識を身につけることが大切です。
2-2. 報酬と税金の関係
Webライターの報酬は、クライアントの種類によって税金の扱いが異なり、企業クライアントからの報酬には通常10.21%の源泉徴収が適用されます。
例えば、報酬10万円なら1万210円が差し引かれ、8万9,790円が振り込まれます。
一方、個人クライアントは源泉徴収の義務がないため、満額が支払われるのが一般的です。
消費税については、原則として年間売上1,000万円以下のWebライターは免税事業者として扱い、消費税を請求しません。
例えば、報酬80万円なら消費税を上乗せせずそのまま請求します。
ただし、インボイス制度により、クライアントがインボイス対応を求める場合、インボイスを発行できる課税事業者になるか協議が必要です。
免税事業者のままでいるか、あえて「課税事業者」となってインボイスを発行できるようにするか、クライアントとも協議を重ねて自分とクライアントにとって最適な方法を選択するようにしましょう。
また、請求書作成時には、報酬額や源泉徴収の有無を明確にし、トラブルを未然に防ぐことも大切です。
2-3. 確定申告が実施される目的
確定申告の主な目的は、所得に基づく適正な税額を計算し、納税額を確定させることです。
個人の所得や控除を正確に申告し、所得税や住民税の額を適切に算出します。
確定申告は社会保障の基盤にも関わるものです。
また、申告により所得が明確になることで、将来の年金や健康保険の計算にも影響します。
3. 【3Step】Webライターの確定申告の手順

確定申告が必要だとわかったら、具体的な手順をおさえておくと安心です。
以下の3ステップで、初心者でもスムーズに申告を進められます。
3-1. 必要書類を準備する
Webライターの確定申告には、次の書類が必要です。
- マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと本人確認書類)
- 源泉徴収票
- 請求書や振込明細
- 経費の領収書
- 医療費控除やふるさと納税の証明書
- クラウドソーシングの取引明細
マイナンバーカードはe-Taxや本人確認に使います。
持っていない場合は、マイナンバー通知カードと運転免許証やパスポートなどの本人確認書類で対応できます。
企業クライアントからの源泉徴収票は、報酬額と源泉徴収額を確認するために必要です。
個人クライアントからの報酬には源泉徴収がないため、請求書や振込明細で収入を証明します。
経費の領収書には、パソコン、通信費、取材費、書籍代などが含まれます。
医療費控除には医療費の領収書、ふるさと納税には寄付金受領証明書を準備しましょう。
クラウドソーシング利用者は、プラットフォームの取引明細を報酬や手数料の証明として保管してください。
領収書は月ごとにフォルダで整理し、Evernoteなどのスキャンアプリで電子化、Excelで日付や金額を記録すると効率的です。
3-2. 確定申告書を作成する
確定申告書は、収入や経費、控除を税務署に報告し、適正な税額を計算するために必要な書類です。
記載する情報は、クライアントからの報酬やクラウドソーシングの取引明細、経費(パソコン、通信費、取材費など)、控除(医療費控除、ふるさと納税、青色申告特別控除など)です。
確定申告書は、会計ソフトや国税庁のツールを使って簡単に作成できます。
会計ソフトを使えば、収入や経費を入力するだけで申告書を自動生成でき、入力ミスも防げ、より効率的な会計管理が可能になるため、初めて確定申告書を作成する方にもおすすめです
例えば、クラウド型会計ソフトのfreeeの副業プラン(月980円)を使えば、スマホで領収書を撮影しての自動入力が可能です。
3-3. 確定申告書を提出する
確定申告書の提出方法はネット・郵便送付・持参の3つがあり、期限は3月15日です。
e-Taxなら、マイナンバーカードとカードリーダーでオンライン完結します。
例えば、e-Taxなら申告書を約3分で提出でき、郵送の場合は、申告書を印刷して税務署に送付します。
送付先は税務署の住所を確認してください。
税務署に直接持参する場合は、平日9時から17時の受付時間に提出します。
2月下旬から3月は混雑するため、早めの対応がおすすめです。
1月から書類を整理し、2月初旬に申告書を作成、2月中旬までに提出するスケジュールなら、混雑を避けられ、ミスも防げます。
例えば、1月に領収書を整理し、2月初旬に申告書を作成、2月15日までにe-Taxで提出すれば、期限直前のストレスがありません。
早めに準備することで、万が一の修正にも余裕が持てます。
4. 白色申告と青色申告!節税効果を比較

確定申告には白色申告と青色申告の2つの方法があり、節税効果や手間が異なります。
どちらが自分に合うか、以下で比較します。
4-1. 白色申告
白色申告は、事業所得または雑所得で申告でき、記帳の手間が少ないのが特徴です。
事業所得には継続的なライティング、雑所得には単発や臨時のライティング(年1~2回の原稿料など)があてはまります。
白色申告は簡易簿記で管理でき、例えばExcelで収入と経費を記録するだけで済みますが、特別控除がなく、節税効果は経費に限られます。
雑所得の場合、青色申告は適用できないため、20万円以上の所得があれば白色申告が唯一の選択肢となります。
4-2. 青色申告
青色申告は、事業所得を持つWebライター向けで、節税メリットが大きい制度です。
事業所得とは、毎月複数のクライアントから報酬を得る場合などの、継続的かつ独立したライティング活動を指します。
青色申告の主なメリットは、最大65万円の特別控除と赤字の3年間繰越です。
例えば、事業所得100万円で複式簿記を採用した場合、65万円の特別控除を受けられ、課税所得は35万円に減ります。
これにより、所得税と住民税の負担が軽減され、節税が可能です。
赤字繰越では、仮に初年度の赤字30万円があった場合、翌年の黒字が50万円あった場合に相殺でき、課税所得を20万円に減らせます。
副業ライターでも、開業届を提出すれば事業所得として青色申告が可能です。
例えば、月3万円の継続的なライティングで年間36万円の報酬を得る場合、事業所得として青色申告でき、節税効果を得られます。
4-3. 青色申告の開始方法
青色申告を始めるには、ライティング活動が事業所得として認められる必要があります。
事業所得と認められるには、契約書や振込明細で継続性を証明することが重要です。
年1回の原稿料5万円のような単発案件は雑所得と判断される場合があるため、一度税務署に「ライティング活動が事業所得に該当するか」を相談して確認しておくと安心です。
手続きは、事業開始から1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。
青色申告承認申請書は、以下のいずれかの期限までに提出します。
- 新規に事業を始めた場合:1月16日以降の事業開始から2ヶ月以内
- すでに事業を行っていて青色申告に切り替える場合:青色申告を始める年の3月15日まで
両書類とも、e-Taxまたは税務署窓口で提出でき、手数料はかかりません。
5. Webライターが確定申告で経費に計上できるものと注意点

経費計上はWebライターの節税の鍵です。
どのような費用が経費として認められるのか、基準や具体例、注意点を初心者にもわかりやすく解説します。
5-1. 経費の基準
経費として認められるのは、業務に必要かつ直接関連する費用です。
パソコン代やインターネット代などはライティングに直結するため、経費として計上できます。
プライベートと業務で併用する場合は、業務の割合で分けることが必要です。
例えば、自宅の家賃10万円で業務使用が30%の場合、3万円を経費として計上できます。
按分比率は業務時間を基に計算されるため、「1日のうち4時間をライティングに使用した」などと記録を残しておくと、税務調査で説明しやすくなるでしょう。
領収書は紙または電子データで5~7年間保管する必要があります。
スキャンアプリで電子化すると管理が効率的です。
整理整頓を徹底することで、経費の妥当性を証明しやすくなり、税務調査時の場合にも対応が可能です。
5-2. 経費の具体例
Webライターが確定申告で節税する際、以下の経費を計上できる可能性があります。
- パソコンや周辺機器(マウス、キーボード、モニターなど)
- 通信費(インターネット代、電話代など)
- ライティング関連の書籍代やセミナー費用
- 取材や打ち合わせの交通費、カフェ代
- クラウドソーシングの手数料
パソコンや周辺機器は、業務に必要な場合に経費計上が可能です。
例えば、15万円で購入した業務用パソコンは、青色申告の個人事業主が「少額減価償却資産の特例」を利用すれば、購入年に全額を「器具備品」として経費にできます。
この特例は、30万円未満の資産を一括で経費計上できる青色申告者向けの制度で、節税効果が高いです。
こうした経費を正確に記録することで、所得を減らし、節税効果を高められます。
5-2. 計上できないものと注意点
Webライターが経費として計上できないものは主に次の通りです。
- 所得税、住民税
- 水道代、ガス代などの光熱費(業務と無関係な場合)
- 電気代、家賃(業務と無関係な場合)
- 家族との外食や趣味の書籍など、私生活の出費
経費として認められるのは、Webライティングの業務に関連する費用のみです。
所得税や住民税、業務と無関係な光熱費、家族との外食や趣味の書籍などは計上できません。
業務でしか使わないもの(例:業務用パソコン)は100%経費にできますが、プライベートと業務で併用するもの(例:自宅の家賃や電気代)は、業務の割合で分ける必要があります。
例えば、家賃10万円の10%を業務用と判断した場合、1万円のみ経費計上可能です。
過大な割合(例:家賃全額)を計上すると、税務調査で否認されるリスクがあります。
業務の割合は、業務時間や使用頻度に基づいて合理的に設定し、計算根拠を記録しておきましょう。
領収書がない現金払いの費用は、証明が難しいため経費として認められない可能性が高いため、注意が必要です。
6. Webライターが確定申告をスムーズに進めるための2つのポイント

確定申告を効率的かつ正確に進めるコツを、契約時の注意点、帳簿管理の2つの視点で解説します。
初心者でも実践しやすい方法をまとめました。
6-1. 契約時の確認を徹底する
クライアントとの契約時に、報酬額、源泉徴収の有無、消費税の扱いを明確にすると、税務トラブルを防ぎやすくなります。
契約書に「報酬10万円、源泉徴収10.21%、消費税なし」と明記すると、支払い時の誤解がなくなるでしょう。
企業クライアントは通常10.21%の源泉徴収を行いますが、個人クライアントは満額を払うことが一般的なため、確定申告時に自分で税金を計算する必要があります。
また、インボイス制度(2023年10月開始)により、年間売上1,000万円以下の免税事業者はインボイスを発行できません。
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を正確に管理するための制度で、インボイス(適格請求書)は、消費税額や登録番号を記載した特別な請求書のことです。
Webライターが免税事業者の場合、インボイスを発行できないため、クライアントが消費税の控除を受けられない可能性があり、報酬減額や契約条件の変更を求められる場合があります。
インボイスを発行するには、税務署に登録申請して課税事業者になる必要があり、消費税の納税義務が生じます。
クライアントがインボイスを求める場合は、事前に協議が必要です。
契約書がない場合、メールでの合意も有効ですが、書面化が理想です。
国税庁のウェブサイトやクラウドソーシングプラットフォームのテンプレートを参考にすると、契約書作成がスムーズです。
6-2. ソフトを活用する
会計ソフトを使えば、収入や経費を入力して月次で確認でき、損益計算書や貸借対照表が自動作成されるため、手作業で入力するより管理が楽になります。
例えば、領収書をスキャンアプリで電子化し、7年間保管します。
簡易簿記なら、Excelで日付・項目・金額を記録するだけで十分ですが、銀行口座やクレジットカードを会計ソフトに連携すると、取引データが自動入力され、ミスを防げるためおすすめです。
また、毎月最終日に領収書を整理する習慣をつけると、年間の収支管理が効率的になります。
7. Webライターの確定申告でよくある質問

確定申告に関するよくある疑問をQ&A形式でまとめました。
副業・本業問わず、Webライターや初心者が知りたいポイントをわかりやすく解説します。
7-1. 確定申告では収入と所得のどちらを使う?
確定申告では「所得」を基準にします。
ちなみに、収入はクライアントからの報酬の総額で、所得はそこから経費を差し引いた金額です。
例えば、報酬30万円(源泉徴収後約27万円)で経費5万円なら、所得は25万円です。
副業の場合、所得20万円超で申告が必要で、源泉徴収された約3万円の一部が還付される可能性があります。
また、収入と経費を日々記録しておくと、申告準備をより効率的に進められるためおすすめです。
7-2. 確定申告はいくらから必要?
副業ライターは所得20万円超、本業ライターは48万円超で確定申告が必要です。
報酬50万円で経費15万円の場合、所得は35万円となり、副業なら確定申告が必要ですが、本業なら不要です。
収入と経費を日々管理しておくことで、申告が必要かどうかがわかりやすくなります。
7-3. 源泉徴収がある場合、確定申告は不要?
源泉徴収があっても、副業の場合は所得20万円超、本業の場合は48万円超の場合は確定申告が必要です。
ただし、源泉徴収された税金は、申告で還付される可能性があります。
報酬30万円(源泉徴収後約27万円)で経費5万円の場合、所得25万円となり、副業なら申告が必要です。
この場合、源泉徴収された約3万円の一部が還付される可能性があります。
7-4. クラウドソーシングの手数料は経費?
ランサーズやクラウドワークスなどのクラウドソーシングの手数料は経費として計上できます。
例えば、報酬10万円で手数料1万円の場合、1万円を経費にできます。
プラットフォームの取引明細をPDFで保存すると、証明が簡単になるためおすすめです。
7-5. 確定申告の疑問はどこに相談すればよい?
確定申告の疑問はさまざまな相談先で解決できます。
例えば、国税庁電話相談(0570-00-5901、受付時間は土日祝日および12月29日~1月3日を除く8時30分~17時00分)や各税務署への電話・訪問が利用可能です。
8. まとめ
Webライターは、副業なら所得20万円超、本業なら48万円超で確定申告が必要です。
申告方法には白色申告と青色申告があり、このうち青色申告を活用すると、最大65万円の控除や赤字繰越で税負担を軽減できます。
疑問は税務署や会計ソフトのサポートに相談すると解決できます。
確定申告を正しく行い、安心してWebライティングを続けましょう。
関連記事
-
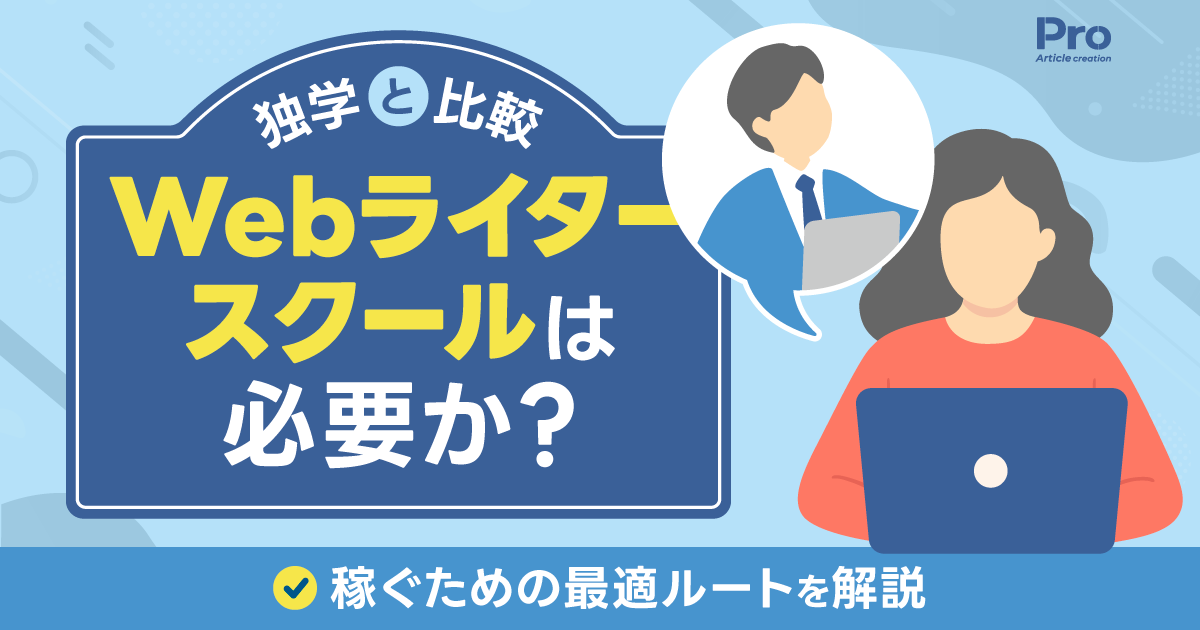
2025.10.08
Webライタースクールは必要か?独学との比較や稼ぐための最適ルートを解説
「Webライターになるためにはスクールが必要?」 「独学でも稼げるWebライターになれるのかな?」 とお悩みではありませんか。 在宅副業として人気のWebライターですが、近年多数のスクールが開講されており、「どのスクールを選ぶべきか」「そもそもスクールは必要か」と迷う方も多いでしょう。 結論からいうと、Webライターになるためにスクールは必須ではありません。最適な学習方法を見つけられれば、独学でも …
- webライター
-

2025.10.05
未経験の主婦が「Webライター」になるには?始め方の最短ルートを7ステップで徹底解説
子育てや家事に追われながらも、「自分の時間を少しでも収入に変えたい」「社会との繋がりをもう一度感じたい」そう願う主婦の方に、Webライターという働き方も1つの選択肢です。 本記事では、未経験からでも在宅で無理なくWebライターを始められる方法を、7ステップで徹底解説。 さらに、収入事情から収入アップの秘訣まで、幅広くまとめました。特別なスキルや自信がなくても大丈夫。 「月3〜5万円を目指すための現 …
- webライター